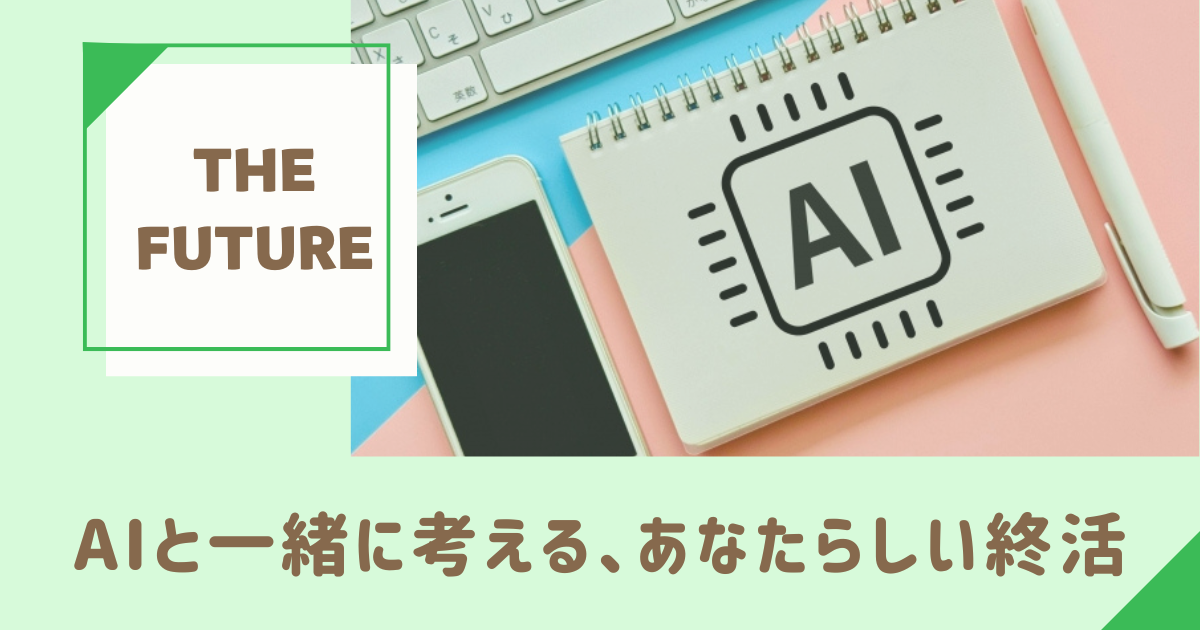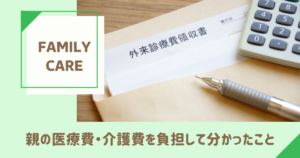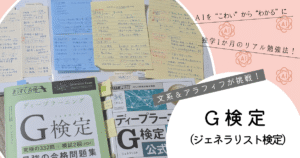【PR】この記事には広告を含む場合があります。
- 大阪万博で感じた「未来の終活」とは?
- AI技術を活用したエンディングノートや見守りロボットの今
- 自分らしい生き方・想いの残し方を考えるヒント
終活って「まだ先の話」「なんだか重たい」と感じて、手をつけられないまま…
といったご相談を、私は日々たくさん受けています。
そんな中で最近、私自身も驚いたのが、「AI」が終活のサポートをしてくれるようになってきたことです。

いつもの終活に、「未来」の視点を少しプラス。
この記事では、私が大阪万博で出会った“アンドロイドとの問いかけ”をきっかけに感じた、「未来の終活」についてご紹介していきます。
「AI×終活って、どんなことができるの?」
「難しそうだけど、ちょっと興味がある」



そんな方にこそ、読んでいただきたい内容です。
【AIと終活】大阪万博で考えた“未来の人生の整え方”とは?
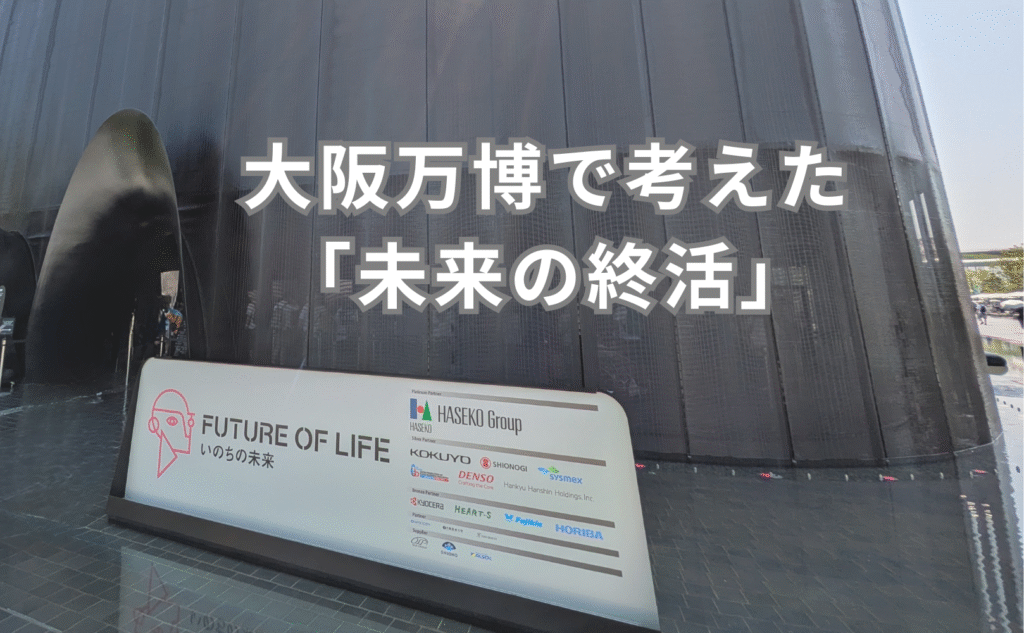
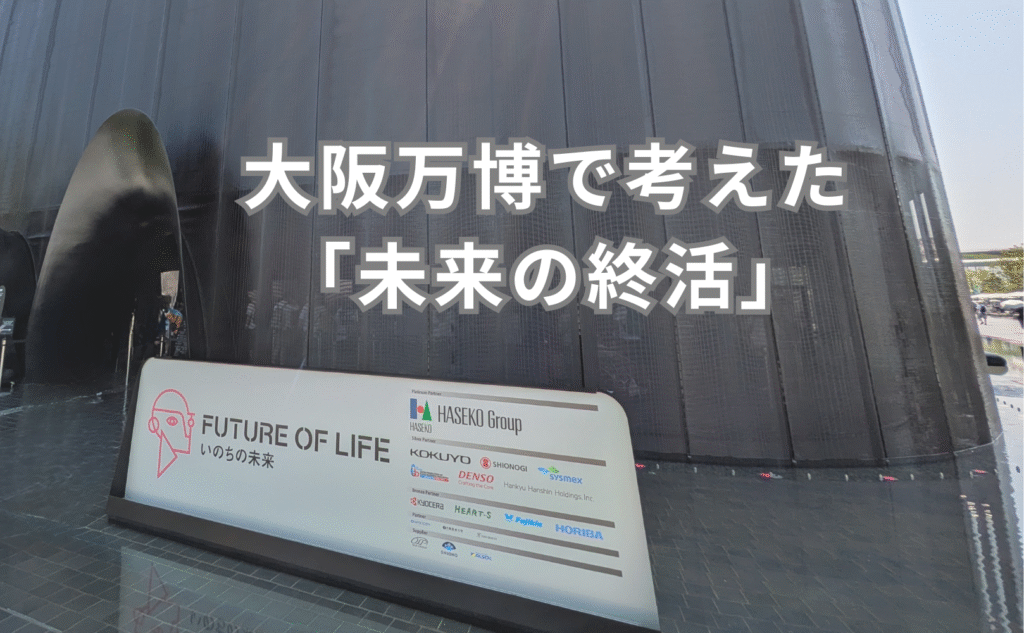
大阪・関西万博「いのちの未来」パビリオンに入った瞬間、私は心を奪われました。
そこに座っていたのは、驚くほど人間にそっくりなアンドロイド。


あまりに自然すぎて、思わず見とれていた私は、うっかり足元のポールにぶつかってしまいました(笑)。
その後しばらく、地味な打撲の痛みが残っていたのですが…それくらい現実との境界が曖昧になる体験だったんです。
アンドロイドからの問いかけがくれた気づき
そして、アンドロイドに迎えられたあと、展示の奥である問いに出会いました。


それは──
「普通に人生を終えるか、それともアンドロイドの体に記憶を移して“存在し続ける”か」



まるでSF映画のような選択肢ですよね。
でも、もしかしたら未来では、こんなことも本当に選べる時代になるのかもしれません。
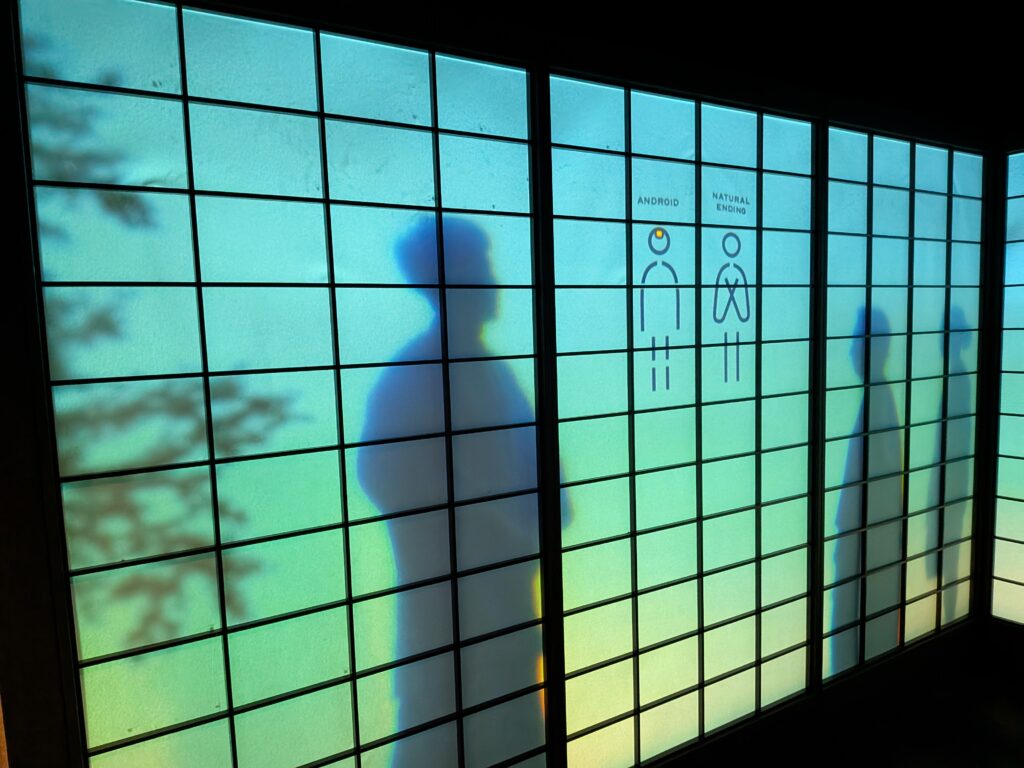
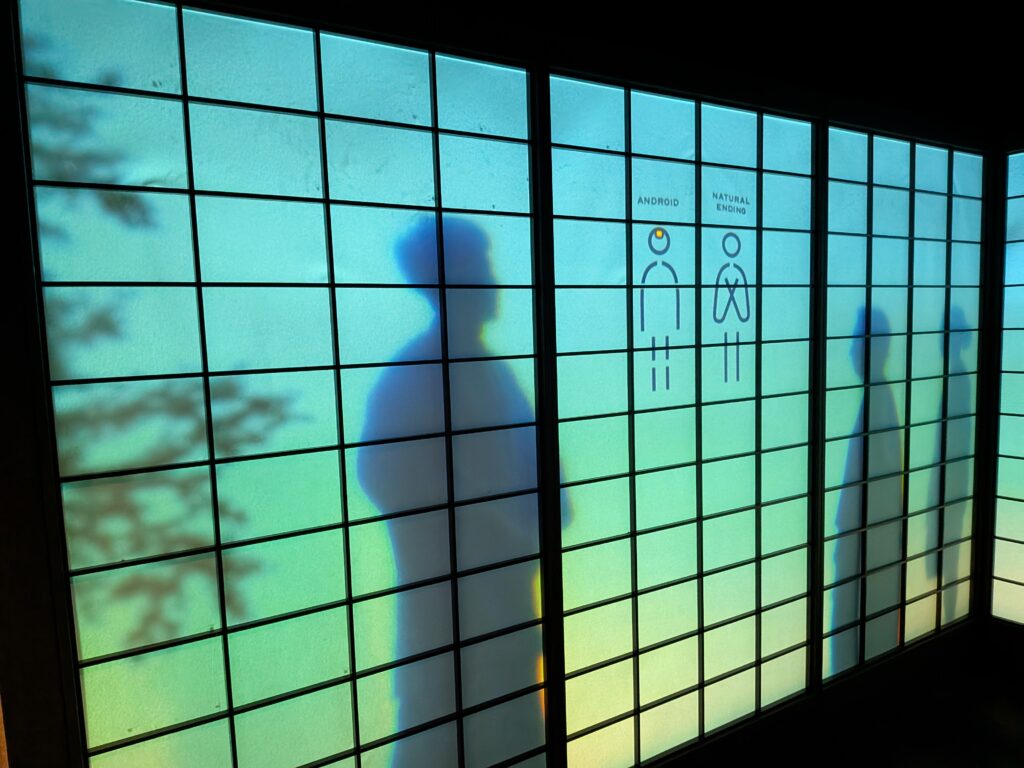
この問いを前にしたとき、ふと自分に問いかけていました。
「私だったら、どちらを選ぶんだろう?」
そして出口の近くの壁に浮かび上がっていた一文が、深く心に刺さったんです。
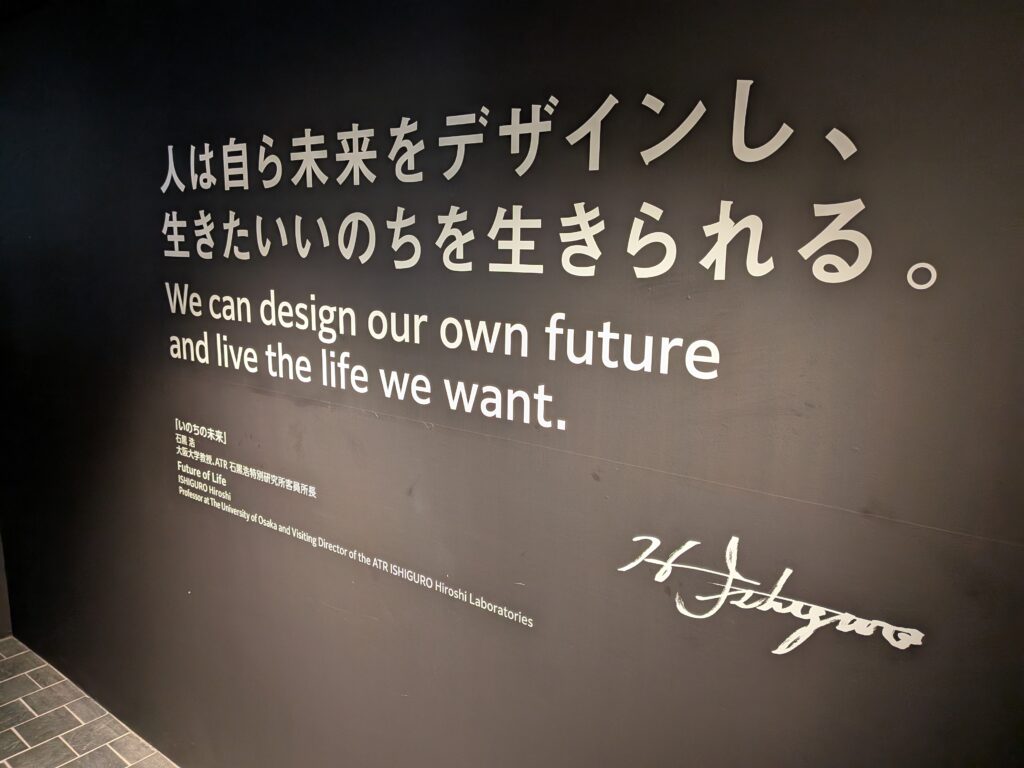
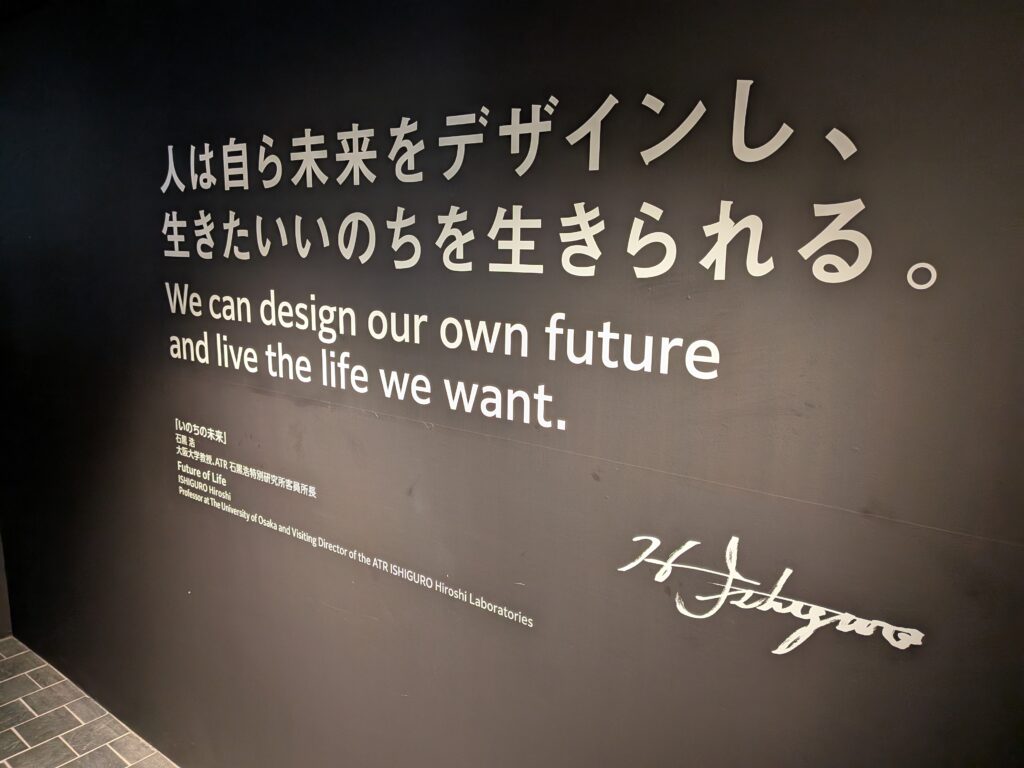
人は自ら未来をデザインし、生きたいいのちを生きられる。
あの言葉の意味をもっと知りたくて、翌日『いのちの未来』の本を手に取りました。
展示だけでは受け止めきれなかった想いや問いが、ページをめくるたびに少しずつ言葉になっていくようで…。



気づけば、最後まで夢中で読んでいました。
100歳の自分を想像したら、終活が“自分ごと”になった





2075年。もし元気に生きていたら、私も夫も100歳です。
「人生100年時代」と言われる今、それはもう“ずっと先の話”ではないんですよね。
「自分の最期をどう迎えるか」──そんなテーマに、少しずつ向き合う時期に入ってきたのだと感じました。
終活と聞くと「死の準備」と思われがちですが、私はちょっと違う見方をしています。
むしろ「これからをどう生きたいか」を考える時間だと思うんです。
たとえば、こんなことを自分に問いかけてみたくなります。
- どんな最期を迎えたい?
- 家族に、どんな想いを残したい?
- 自分らしい人生って、どんな選択をしたときに言える?
万博での体験は、こうした問いを自然に引き出してくれるきっかけになりました。
未来のテクノロジーに触れたからこそ、逆に「人間らしさ」や「心の奥にある希望」が鮮やかに浮かび上がってきたんです。
そのとき、終活は“前向きな時間”にもなるんだと実感しました。
AIがもっと身近になるこれからの時代。
私自身、「AI×終活」というテーマに出会ったことがきっかけで、興味がどんどん深まり、なんとそのまま勢いで G検定(ジェネラリスト検定) にチャレンジしてみたんです。



結果は……合格!
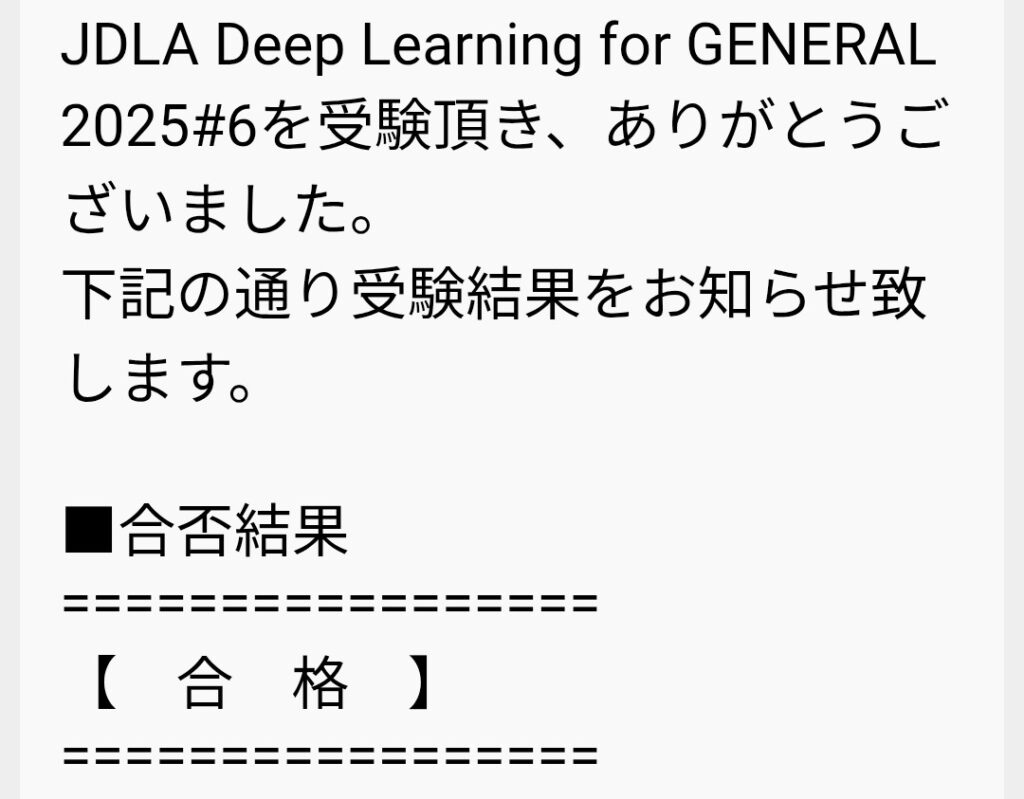
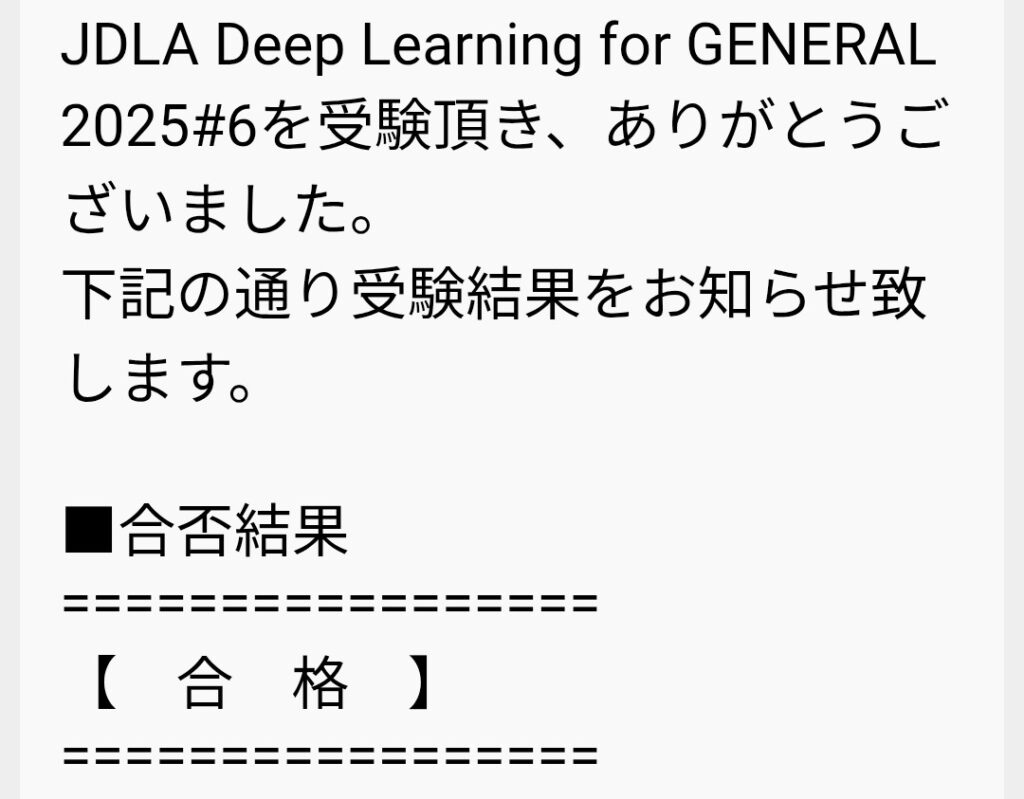
難しそうに見えるAIも、知ってみると意外と身近で、終活だけでなく、日々の生活にも役立つ視点がたくさんあると感じました。
こんな風に、「興味」から一歩踏み出してみることで、未来との向き合い方が変わるかもしれませんね。



G検定(ジェネラリスト検定)は、こちらで詳しく紹介しています。
▶ G検定は難しすぎる?文系・アラフィフでも独学1か月で合格できた話
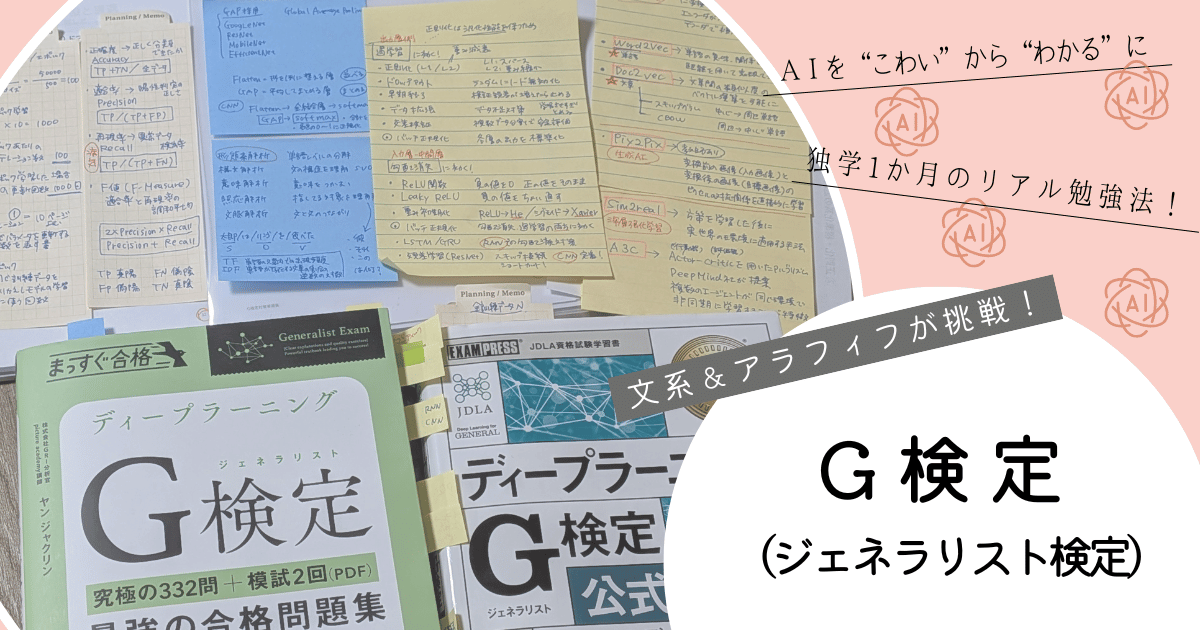
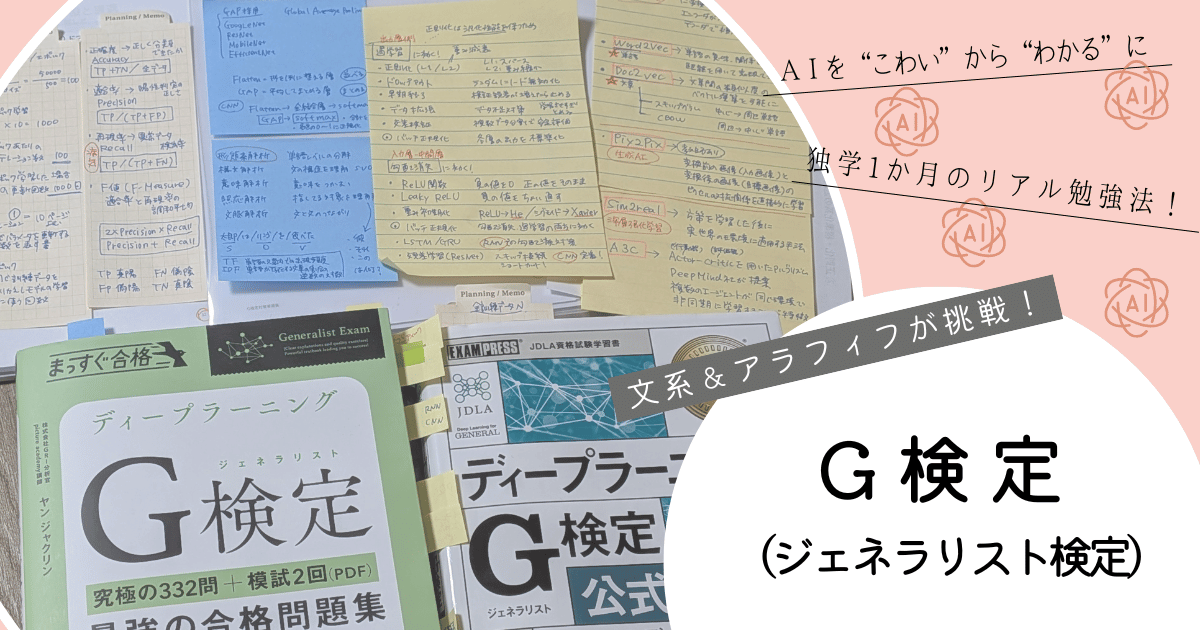
AI×終活の今|私たちにできること、始められること


「AI」と聞くと、少し難しそうなイメージを持つ方も多いかもしれません。
でも実は、私たちの暮らしの中でも、終活にまつわる場面で少しずつ活用が始まっています。
たとえば
- 離れて暮らす家族をつなぐ「見守りロボット」
- 気持ちを言葉にするのを手伝ってくれる「AI聞き書き」
- 未来に想いを託せる「デジタル遺影」や「AIアバター」
こうした技術は、決して特別な人のためのものではなく、「想いを残したい」「つながっていたい」という気持ちに、やさしく寄り添うための道具なのです。
ここからは、私自身が体験したことや実際に使ってみたサービスを交えながら、「今の時代にできる、AI×終活」をご紹介していきます。
AI見守りロボットで安心とつながりを
一人暮らしの高齢者が増える中で、家族にとって心配なのが「ちゃんと元気で過ごしているかな?」ということ。



そんな時に役立つのが、 AI搭載の見守りロボット です。
センサーやカメラなどで安全をチェックするだけでなく、話し相手にもなってくれるのがポイント。
「今日は体調どう?」
「メッセージが届いてますよ」
そんな何気ない会話ができることで、孤独感が減り、心も支えられるようになってきています。
“ただ見守る”存在から、“寄り添うパートナー”へ──AIはそんな進化をしています。
ちなみに、一人暮らしの母も BOCCO emo (ボッコエモ)LTEモデル Powered byネコリコ を使っています。



声やメッセージでつながれるので安心感がありますよ。


今回ご紹介した ネコリコ版BOCCO emo のほかにも、高齢者向けの話し相手ロボットはさまざまな種類があります。
「もっと比較して選びたい」「他のロボットも知りたい」という方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
▶ 話し相手ロボットを徹底比較!おすすめ5選と選び方のポイントを詳しく紹介しています。


AIと一緒に作る、あなたらしいエンディングノート
「何を書いたらいいかわからない」「うまく言葉にできない」
そんな方でも、AIの力を借りれば、あなたらしいエンディングノートが自然に形になっていきます。
ここでは、実際にAIを使って“話すだけ”で手紙をつくる体験をご紹介します。
現在は「AIレター(AIが手紙の作成を手伝ってくれるサービス)」や「Voice Legacy(音声を残せる海外発のサービス)」といった専用サービスも。
しかし、まだ発展途上という印象もあり、現時点では使い方が難しかったり、日本語対応が不十分だったりするものもあります。
そんな中で、実際に私自身が「これなら使える」と思ったのが、AIを活用した方法です。
実際に、ChatGPTに「家族へ残す手紙を作りたいのでインタビューしてください」とお願いしてみたところ、このように質問形式で優しく導いてくれました。
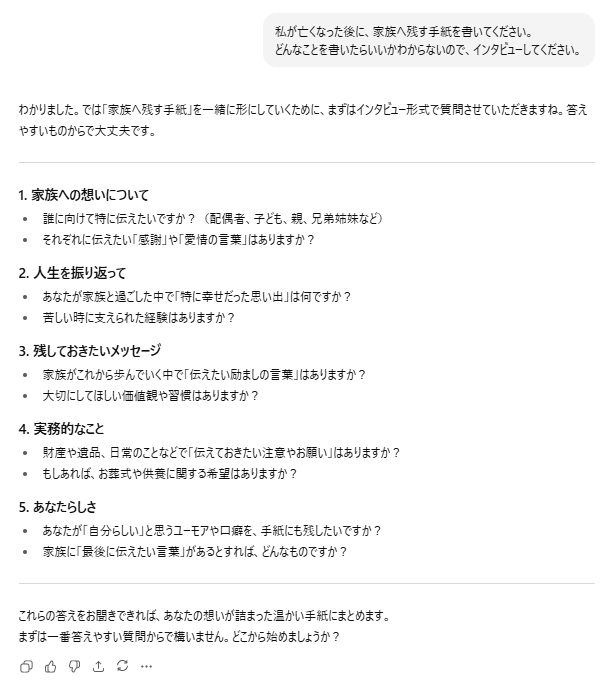
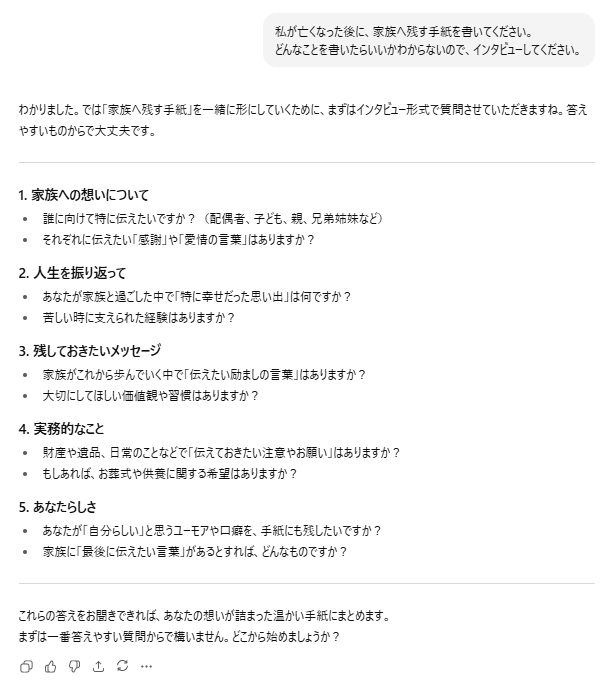
このように、一つひとつの問いに答えていくだけで、あなたらしい“想いの手紙”が自然と形になっていきます。
最初はうまく言葉にならなくても大丈夫。
AIが“聞き役”となって、あなたの気持ちを引き出してくれます。
スマホでも気軽に使えるので、気になる方はぜひ一度、AIとおしゃべりするつもりで試してみてください。



あなたの中にある想いは、ちゃんと言葉にできますよ。
デジタル遺影・AIアバターで「想いを残す」という選択肢
最近では、AIを活用して、生前の表情や声をデジタルで残す「デジタル遺影」や「AIアバター」といった取り組みも出てきています。
写真のように“飾るだけ”の遺影ではなく、まるで本人と会話しているような形で、生きた記憶や想いを残せるのが特徴です。
まだ一部の企業や研究機関による試みが中心ですが、技術はどんどん進化しており、「未来の終活」のひとつとして注目されています。
例えば、亡くなったおじいちゃんのAIアバターが、こんな風に語りかけてくれる未来も近いかもしれません。
「○○よ、元気にしてるか? お前が笑ってると、わしも嬉しいよ」



まるで、心の中にずっと生き続けてくれるような感覚ですね。
最近では、こうしたAIアバターを無料で簡単に作れるサービスも出てきています。
Canva (キャンバ)は、デザインの専門知識がなくても、誰でも簡単におしゃれなデザインを作れるオンラインツールで、私もよく使っています。



Canvaの「AIアバター」機能を使えば、3分で作れます。
※注意:音が出ます。
もちろん、こうした取り組みには賛否もあります。
「そこまでしなくてもいい」「少し怖いかも」と感じる方もいらっしゃると思います。
でも一方で、“残したい言葉”や“伝えられなかった想い”を届けられる手段として、やさしい可能性も秘めていると私は感じています。
AI×終活は、無理に取り入れるものではありません。
「自分らしい生き方・伝え方」を選ぶための、ひとつの選択肢として、未来のヒントになれば嬉しいです。



どんな未来を残したいか、考えてみる時代が来ていますね。
AI×終活の始め方・活用例がわかるQ&A【初心者向け】
ここからは、読者の方からよくいただく質問をもとに、「AI終活って実際どうなの?」にお答えしていきます。
- AIを活用した終活にはどんなものがあるの?
-
代表的なものに、見守りロボット(例:ネコリコ版 BOCCO emo)、AIエンディングノート、AIによる手紙作成(聞き書き)、デジタル遺影やAIアバターなどがあります。
これらは「想いを残す」「つながる」ためのサポートとして注目されています。
- AI終活って難しそうだけど、誰でもはじめられる?
-
はい、最近ではスマホひとつで使えるサービスも増えてきており、特別な知識がなくても気軽に始められます。
ChatGPTのようなAIに「家族へ手紙を書きたい」と話しかけるだけで、あなたらしい言葉を引き出してくれます。
- AIアバターやデジタル遺影って、ちょっと怖くない?
-
初めて聞くと戸惑うかもしれませんが、「伝えたい気持ち」を残すための手段として、やさしい可能性も秘めています。
あくまで選択肢のひとつなので、無理に取り入れる必要はありません。
あなたらしい方法で大切な人に想いを伝えることが大切です。
- エンディングノートって、AIで作れるの?
-
はい。最近では、AIに話しかけるだけでエンディングノートの下書きが作れるサービスが登場しています。
ChatGPTなどを使い、質問形式で答えながら作成するのもおすすめです。
【まとめ】終活は“これからをどう生きるか”を考える時間
終活は「死の準備」ではなく、これからをどう生きたいかを考える時間。
AI技術の進化によって、その向き合い方は大きく広がり、もっと自由で、もっとやさしいものになってきています。
見守りロボット、エンディングノート、デジタル遺影──どれも特別な人のためではなく、「想いを伝えたい」「誰かとつながっていたい」という気持ちに寄り添うためのツールです。
たとえテクノロジーがどれだけ進化しても、最後に残るのは、人と人とのつながりや、心に残る言葉なのかもしれません。
大阪・関西万博での出会いをきっかけに、私は“AI×終活”というテーマに関心を持つようになりました。
私自身も、G検定に挑戦したり、AIロボットとゲームで本気勝負したりしながら、少しずつAIとの距離が縮まってきた気がします。
未来の終活も、最初の一歩は“ちょっとした好奇心”から始まるのかもしれません。
気になった方は、まずは「AIに聞きながら作る手紙」から試してみてくださいね。



あなたらしい終活、きっと“みがる”に始められますよ♪